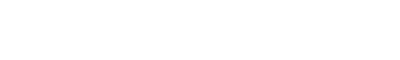第74期支部長
名古屋大学
工学研究科マイクロ・ナノ機械理工学専攻
教授, 工学博士
梅原 徳次
経歴:1988年3月 東北大学大学院工学研究科(機械工学専攻)
博士後期3年の課程修了,工学博士,
1988年 東北大学助手,講師及び助教授,
2000年 都立科技大准教授,2002年名古屋工業大学教授,
2004年 名古屋大学大学院工学研究科教授(現職)
2008年 東海支部庶務幹事,2015年機素潤滑設計部門長,
2018-19年 理事
1 はじめに
このたび,第74期東海支部支部長を拝命した名古屋大学の梅原徳次と申します.責任の重大さに身の引き締まる思いです.日頃より,東海支部の諸活動にご支援賜り,深くお礼申し上げます.今期は,豊田中研高尾副支部長,名大奥村庶務幹事をはじめとする幹事,商議員の皆さまにお力添え頂き,会員の皆さまに,より一層ご満足頂ける支部活動を目指して参りますので,宜しくお願い申し上げます.
2 東海支部の現状の活動と時代に合わせた変革について
東海支部は1952年に設立され,今年で74期目を迎えます.東海地区は日本の「ものづくり」の中心地であり,航空・宇宙産業や自動車産業をはじめ,工作機械,金属・セラミックス材料,機械要素など有力な産業が集積しております.また東海支部は,約80社の特別員(法人会員)をはじめとして産官学から多くの方々にご参加頂いております.
支部会員数は3700名程度であり,関東,関西に次いで3番目の会員数ですが,学会全体の傾向と同様に会員数の減少が続いています.会員数の減少は2000年ごろから始まりました.これは,インターネットが普及し非会員の方でも情報が容易に入手可能になり,企業及び個人が学会参加の効果を判断した結果と思われます.さらに,コロナ禍が始まりました2020年より減少率が増加しております.これは,コロナ禍でオンラインが整備され,ウエビナーをはじめ講演による情報もさらに容易に入手出来やすくなったためと考えられます.これらの原因のためか,学生員からの正員への継続率が低く,20代から40代の最も仕事に活用できる年代の正員が少ないことが問題となっています.これらの機械工学で活躍している方に対する支部活動として,講演会や,見学会,研究会などがありますが,どのようにそれぞれの活動を更に魅力的にするかが課題です.
日本機械学会全体の役割として,機械工学の発展の促進や,新しい機械工学の技術成果の社会へ還元があり,研究会や講演会による情報提供は勿論重要です.
但し,支部としては,情報提供だけではなく,産業界と大学・公的研究機関とは,専門や業種を超えたさらなる交流が望まれており,本支部もその一翼を担える機能,役割を果たすことが一層必要ではないかと考えています.特に,コロナ禍以降,大部分の情報がオンラインで提供されるため,逆に,大型の機械工学の施設や設備の見学などの体験や,個別の案件に対する対面での深い討論の場が不足しているように思われます.
本東海支部におきましては,幸いにも機械工学に関する多くの企業が身近に集積しており,機械工学の現状の実物を見ること及び優れた開発者や研究者と交流することが可能であります.
そこで,まずは幹事会から,対面を重視し,サロン的な雰囲気でコロナ禍以後の新しい時代に即した,他では体験できないことが体験できる魅力的な企画を立案・実施できればと考えています.
3 おわりに
東海支部では,3月開催の支部定時総会・講演会および卒業研究発表会をはじめとする各種イベントや諸活動を,コロナ禍後の新しい時代に対応した内容に変え,さらに会員の方に魅力的であるように開催して参ります.皆さま方におかれましては,これらの活動を活発で意義あるものとするべく積極的なご参加とご支援を頂きますよう,なにとぞ宜しくお願い申し上げます.